/
見過ごせない"えきねっと"予約不整合
アプリで出来ることがWEBで出来ない!
北陸新幹線の東京~金沢の往復予約
こんな基本的なことは出来て当たり前。アプリでは簡単にできる。パソコン広げてブラウザでやろうとするとエラー!になる。そんな馬鹿な。
そう。JR東日本は"そんな馬鹿な"のだ。
/
WEBサイトで出来ない予約がアプリを使うと出来る。という単純な話で、何処かにその旨の注意書きが出ていた。注意書きを出して置けば免罪符になるとでも思っているのだろうか。全くのバカの照明そのものだ。
/
ブラウザで予約の状況をチェックしているとエラーとか注意書きが色々出て来るが、実際に意味があるのかどうかも怪しいものだ。
/
JR東日本・新幹線・予約
JR東日本・北陸新幹線・予約
検索すると「えきねっと」と出て来る。
チケットレスとかも出て来るが、高齢者を混乱させないかな。スマホも時々怪しくなる人には無理かも。
*

えきねっとに
会員登録
https://www.eki-net.com/Personal/Top/Index
https://www.eki-net.com/Personal/member/wb/UserCommon/Guidance

新幹線eチケットの
お申込み※
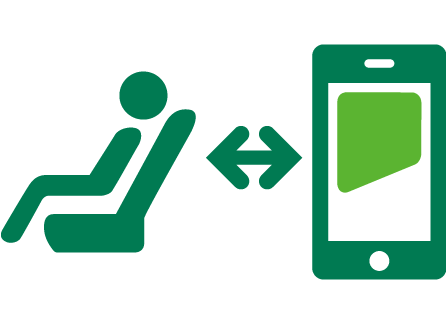
乗車人数分の
ICカードを紐づけ

紐づけが完了した
ICカードで乗車
*
*
/
新横浜から東海道新幹線で東京に入って、東京から敦賀まで北陸新幹線で行ってみる。
と、これがスムーズに出来ない。
新横浜から東京までは自由席で構わない。新横浜で20%以上が降りてしまうから空席ばかり。
問題は、今尚、JR東海とJR東日本の仲たがい。客の利便を押しのけて角を突き合わせている。表向きは大人の発言をしていても、現場の実態は私鉄との乗り換え・乗り継ぎよりも不便な状況。
国交大臣が何も考えない馬鹿と直ぐに分かる。公明党ってこんなものですよ。
/
職場が都心にあった時は毎日JRの世話になるのに。
職場がド田舎に変わるとJRは殆ど縁が無い。接点があっても景色の中の1パーツ。満員電車に無縁なことがこれほど素晴らしいとは思わなかった。
それが全く残念なことに 新幹線で遠地へ出掛けることになった。空港も無いから実質的に新幹線が唯一の選択。
始めての新幹線旅行。旅程は3泊4日~5泊6日の程度。予定日程まであまり時間が無いので、少し焦っている。お金も余り無い。とは言え自由席は絶対無理。
異動プランを考えるのに今流行りのAI(Gemini+Copilot)を使おうとしたら全くの役立たず。
*
JRは外からアクセスするなど全くなかったが、DX化に取り組んでいるようで、アクセスする間口が極端に狭い。そのくせ分かり難い。いつものお客さんが何時ものように使う前提でシステムを組んでいる。例外処理は受け付けていないに等しい。最寄り駅に電話も出来ない。問合せセンターに回される。そして延々待たされる。駅の窓口も幾つもの端末が並んでいるだけ対人対応は1人の人がいつも誰かと込み入った話をしている。田舎に来たらこうなると分かっていても残念というか自己嫌悪に陥る。官製サービス業の伝統が色濃く残っている。
家に戻ってネットを繋いでみる:
/
予約サイト
先ずは予約サイト。これが難しい。JR東日本・JR東海・JR西日本。何処か一か所から全部の予約が出来ないのかな。
⇒
できない。馬鹿みたい。旧国鉄が顧客志向でなかったことがよく分かる。顧客より部門間の競争。霞が関と同じ。JRになっても縦割りDNAは何も変わらない。恥ずかしくないのかな。
/
- 「えきねっと」と「新幹線eチケット」の2つがあるようだ。
- 駅ネットの「URL」が暗号化されているような滅茶苦茶。
- 予約の設定データを入れるといきなりエラー。「同時に複数のページは開けない」と来た。最初に言え!。
- 再度データを入れて検索すると幾つかプランが出て来るがJR東海(新幹線)を利用するものは出てこない。全部JR東日本の列車。電車で繋いでいきたいらしい。国鉄分割してもう何十年も経過しているのに未だに顧客本位が実現していない。歴代の国交相が馬鹿の証拠。昨今は公明党の独り占めだから公明党の馬鹿が漏れ出ている。
- 「東海道」と「北陸」の東京駅乗り継ぎは出来ないようだ。★★★
/
- Suicaで新幹線に乗れるとあるがその対象は「東北・北海道、上越、北陸、山形、秋田」だけで、「東海、西日本、九州」は含まない。★★★
/
EX予約
- 会員制(年会費が掛かる)で割安料金。リピーター向け。★★★
- 「東海、西日本、九州」チケットレス(電子マネー?)乗車。会員登録必要。無料。クレカが必要。
/
縦割りJRには呆れるが、もしJR東海JR東日本の東京駅乗り継ぎの可能性があるならSuicaを使ったチケットレス乗車だろう。
Suica利用の想定外を口実に現場でトラブル可能性もある。リカバリーの方法が現場駅員も良く分かっていないと足止めを食らって電車に乗り損なうリスクもある。
/
アカウント
スマートEX:これはJR東海のようだ。
新規会員登録を始めたが登録情報が多すぎる。もたもたしているとタイムアウトで最初からやり直し。必要以上に情報収集する企業って信用置けないけど、JR東海までがそういうレベルとは驚く。何年経っても頭は国鉄DNAに毒されたまま。リニアでもたついている理由も同じ本質かも。
クレカ情報とSuica情報も入れる。JRはいずれも見苦しいばかりの囲い込みをやっている。エクストラなサービスは系列のクレカでないと駄目ですの類も。
- メールアドレス:結局は登録に使うものになる。Suicaでもメアドを登録しているなら、混乱の無いように同じメアドを登録すべきだろう。マルチアカウントの時代は返って混乱させられることも。<Suicaと同じメアドを使え!>
- クレカの登録ではやはりSuicaに連携させているクレカを使うこと。多分トラブル時の混乱が少なくて済みそうだ。
◆
初めての新幹線|初めてのSuica旅行
回答案を表示
新幹線とSuicaでの初めての旅行、楽しみですね!
新幹線とSuicaを使った初めての旅行、ワクワクしますね! 今回は、初めてのあなたでも安心して新幹線旅行を楽しめるように、基本的なことから便利な情報までご紹介します。
新幹線に乗る前に知っておきたいこと
新幹線とは?
日本の高速鉄道で、主要都市間を短時間で結んでいます。快適な座席、車窓からの美しい景色など、日本の旅を代表する交通手段です。
新しいウィンドウで開く
www.n-sharyo.co.jp
新幹線
Suicaとは?
JR東日本のICカードで、乗車券や定期券として利用できます。チャージして利用するプリペイド式なので、小銭を持ち歩く必要がありません。
新しいウィンドウで開く
www.amazon.co.jp
Suica
新幹線に乗るための準備
きっぷの購入:
みどりの窓口: 駅にある有人窓口で、希望の日時、区間、座席などを指定して購入できます。
券売機: 駅にある自動券売機で、タッチパネル操作で簡単に購入できます。
インターネット: JR東日本「えきねっと」などの予約サイトで、事前に予約して座席を確保できます。
Suicaのチャージ:
駅のチャージ機やコンビニなどで、現金やクレジットカードでチャージできます。
座席の指定:
自由席: 空いている席に座ることができます。
指定席: 事前に座席を指定できます。
荷物の持ち込み:
大きな荷物がある場合は、事前に座席指定時に荷物置き場の有無を確認しましょう。
新幹線に乗るとき
改札口を通る
乗車券と特急券: 改札口で、乗車券と特急券を同時に駅員に見せます。
Suica: Suicaを改札機のタッチパネルにかざします。
新しいウィンドウで開く
travel.watch.impress.co.jp
新幹線改札
車内での過ごし方
座席: 指定された座席に着席し、快適な旅を楽しんでください。
電源: 一部の車両にはコンセントが設置されています。
車内販売: 飲み物や軽食を購入できます。
Suicaの便利な使い方
新幹線eチケット: スマートフォンで予約し、Suicaで改札を通るだけで乗車できます。
タッチでGo! 新幹線: Suicaのチャージ残高で、自由席の新幹線に乗車できます。
新幹線旅行を楽しむためのヒント
旅行計画: 行き先、日程、交通手段などを事前に計画しましょう。
持ち物: 切符、Suica、現金、地図、スマートフォンなど、必要なものを忘れずに持ちましょう。
乗り換え: 新幹線と他の交通機関を乗り継ぐ場合は、事前に乗り換えルートを確認しましょう。
駅弁: 新幹線車内で楽しめる駅弁もおすすめです。
まとめ
新幹線とSuicaを使った初めての旅行、ぜひ楽しんでください! 少しでも不安なことがあれば、駅員さんに気軽に声をかけてみましょう。
新しいウィンドウで開く
shin-yoko.net
新幹線車内
新しいウィンドウで開く
foods.jr-cross.co.jp
駅弁
新しいウィンドウで開く
www.jalan.net
日本の風景
この情報があなたの初めての新幹線旅行の役に立てば幸いです。
さらに詳しい情報を知りたい場合は、以下のキーワードで検索してみてください。
新幹線 乗り方
Suica 使い方
新幹線 えきねっと
新幹線 車内設備
駅弁 おすすめ
何か質問があれば、お気軽にご質問ください。
追加で知りたい情報があれば教えてください。例えば、
特定の路線の情報を詳しく知りたい
新幹線でのマナーについて知りたい
旅行先の情報を知りたい
など
あなたの質問に合わせて、より詳しい情報を提供します。
また、画像の追加も可能です。例えば、
新幹線の車内の様子
駅弁の種類
旅行先の観光スポット
など
どのような画像が必要か教えていただければ、可能な限りご用意します。
必要なアプリとアカウントを教えてください。
回答案を表示
新幹線とSuicaを利用した旅行で役立つアプリやアカウントについて、詳しくご説明します。
新幹線旅行で便利なアプリ
1. JR東日本アプリ
主な機能:
駅情報検索: 最寄りの駅の情報、時刻表、乗り換え案内などを調べることができます。
切符購入: 一部の列車の切符をアプリから購入できます。
Suicaの管理: Suicaの残高確認、チャージ、履歴確認などが可能です。
駅ナカ情報: 駅周辺の店舗や施設の情報も得られます。
2. モバイルSuicaアプリ
主な機能:
Suicaの管理: Suicaの残高確認、チャージ、履歴確認などが、JR東日本アプリよりも詳細にできます。
タッチでGo!新幹線: 事前登録により、Suicaのチャージ残高で新幹線自由席に乗車できます。
Apple Pay/Google Payとの連携: Apple PayやGoogle PayにSuicaを登録して、スマートフォンでの決済が可能です。
3. 新幹線eチケットサービスアプリ
主な機能:
新幹線チケットの購入: スマートフォンで簡単に新幹線チケットを購入できます。
モバイルSuicaとの連携: モバイルSuicaでチケットレス乗車が可能です。
予約確認: 購入したチケットの予約内容を確認できます。
4. その他の便利なアプリ
駅すぱあと: 乗り換え案内アプリとして人気です。新幹線だけでなく、他の交通機関との乗り換えも調べられます。
Googleマップ: 地図アプリですが、公共交通機関のルート検索も可能です。
新幹線旅行で便利なアカウント
1. JR東日本アカウント
主な用途:
JR東日本アプリの利用: 上記のJR東日本アプリの機能を利用するために必要です。
えきねっと: 新幹線の予約・発券サービスを利用できます。
2. モバイルSuicaアカウント
主な用途:
モバイルSuicaの利用: モバイルSuicaアプリを利用するために必要です。
アプリ・アカウントの選び方
利用頻度: 頻繁に利用する場合は、複数のアプリをインストールしておくと便利です。
機能: 必要な機能が揃っているか確認しましょう。
連携: 他のアプリやサービスとの連携がスムーズに行えるか確認しましょう。
まとめ
新幹線旅行を快適にするために、これらのアプリやアカウントを有効活用しましょう。事前にアプリをインストールし、アカウントを作成しておくことで、スムーズな旅行が楽しめます。
ご自身の旅行スタイルに合わせて、最適なアプリやアカウントを選び、快適な新幹線旅行をお楽しみください!
さらに詳しい情報を知りたい場合は、以下の点について教えてください。
旅行の目的: ビジネス、観光、それとも両方ですか?
利用する新幹線: 東海道新幹線、東北新幹線など、どの新幹線を利用しますか?
旅行期間: いつからいつまで旅行しますか?
利用する交通機関: 新幹線以外にも、飛行機やバスなどを利用しますか?
これらの情報に基づいて、より具体的なアドバイスをさせていただきます。
例えば、
ビジネス利用: 新幹線eチケットサービスを活用し、スムーズな出張を実現できます。
観光利用: 駅すぱあとを使って、観光スポットへのアクセスを計画できます。
お気軽にご質問ください。
旅行エリアはJR東日本からJR西日本、JR東海にまたがりますが、全てJR東日本のアカウントから予約などできますか。
回答案を表示
JR各社のアカウントについて、詳しくご説明します。
結論から言うと、JR東日本、JR西日本、JR東海と、会社が異なるため、それぞれの区間を予約する際には、原則として各社のアカウントが必要となります。
なぜ各社のアカウントが必要なの?
予約システムが異なる: 各社で予約システムが異なり、互換性がないためです。
運賃体系が異なる: 各社で運賃体系が異なるため、一括での計算が難しいです。
割引制度が異なる: 各社で割引制度が異なるため、一括での適用が難しいです。
跨線区間の予約方法
では、複数のJR会社を跨ぐ旅行の予約はどうすれば良いのでしょうか?
各社のウェブサイトで別々に予約:
最も一般的な方法です。出発駅と到着駅に合わせて、各社のウェブサイトで予約を行います。
例えば、東京駅から新大阪駅まで行く場合、東京駅~名古屋駅まではJR東日本の「えきねっと」、名古屋駅~新大阪駅まではJR東海の「EX予約」でそれぞれ予約します。
旅行代理店に依頼:
旅行代理店では、複数の会社の切符をまとめて手配してくれることがあります。
特に、複雑な旅程や、複数の交通機関を組み合わせた旅行の場合には便利です。
JR東日本のアカウントの活用
JR東日本のアカウントは、主にJR東日本のエリア内での予約や、Suicaの管理に利用されます。他のJR会社のエリアの予約には直接利用できませんが、以下の点で役立ちます。
Suicaの利用: JR東日本のエリア内での移動にはSuicaが便利です。
えきねっとの利用: JR東日本の新幹線や在来線の予約に利用できます。
JR東日本グループのサービス利用: JRE POINTの貯め方や使い方など、JR東日本グループのサービスを総合的に利用できます。
まとめ
JRの跨線区間の旅行は、各社のウェブサイトで別々に予約するのが一般的です。JR東日本のアカウントは、JR東日本のエリア内での旅行をより快適にするためのものです。
よりスムーズな旅行のために
事前に旅程を計画: 各区間の運賃や所要時間を比較し、最適なルートを選びましょう。
各社のウェブサイトに会員登録: 利用するJR会社のウェブサイトに事前に会員登録しておくと、予約がスムーズに行えます。
旅行代理店に相談: 複雑な旅程の場合は、旅行代理店に相談してみるのも良いでしょう。
その他
JRパス: 日本全国のJR線が乗り放題になるJRパスも検討できます。ただし、利用条件や料金などが細かく設定されているので、事前に詳しく調べてみましょう。
スマートEX: JR東海の会員制割引サービスです。JR東海のエリア内だけでなく、一部のJR西日本の新幹線も利用できます。
ご自身の旅行計画に合わせて、最適な方法を選んでください。
もし、具体的な旅行計画があれば、より詳しいアドバイスが可能です。例えば、
出発駅と到着駅
旅行期間
利用したい列車の種類
重視する点(料金、時間、座席など) などを教えていただけると、より的確な情報提供ができます。
日本、長野県松本市新村
新横浜⇒(東海道新幹線)→東京⇒(北陸新幹線)→福井のルートの予約は、JR被害市日本から出来ます。往復になります。
回答案を表示
新横浜~東京~福井間の往復新幹線の予約について
JR東日本エリアからJR西日本エリアへの跨線区間の新幹線予約は、原則として各社のウェブサイトで別々に行う必要があります。
なぜ別々に予約する必要があるのか?
予約システムが異なる: 各社で予約システムが異なり、一括での予約ができません。
運賃体系が異なる: 各社で運賃体系が異なり、一括での計算が難しいです。
割引制度が異なる: 各社で割引制度が異なり、一括での適用が難しいです。
予約方法
1. JR東日本区間(新横浜~東京)の予約
えきねっと: JR東日本の会員制ネット予約サービスです。事前に会員登録を行い、区間、日時、座席などを選択して予約します。
新しいウィンドウで開く
www.eki-net.com
えきねっとのトップページ
2. JR西日本区間(東京~福井)の予約
EX予約: JR東海の会員制ネット予約サービスですが、JR西日本の区間も予約できます。同様に、事前に会員登録を行い、区間、日時、座席などを選択して予約します。
新しいウィンドウで開く
expy.jp
EX予約のトップページ
予約時の注意点
会員登録: 各社のウェブサイトに会員登録が必要です。
区間設定: 出発駅と到着駅を正確に設定しましょう。
座席指定: 自由席、指定席、グリーン車など、希望の座席を選びます。
支払い方法: クレジットカード、電子マネーなど、利用可能な支払い方法を選びます。
予約変更・キャンセル: 必要に応じて、各社のウェブサイトから変更やキャンセル手続きを行います。
その他
旅行代理店: 各社のウェブサイトでの予約が難しい場合は、旅行代理店に依頼することも可能です。
JRパス: 日本全国のJR線が乗り放題になるJRパスも検討できますが、利用条件や料金などが細かく設定されているので、事前に詳しく調べてみましょう。
まとめ
新横浜から福井までの往復の予約は、JR東日本区間とJR西日本区間に分けて、それぞれ「えきねっと」と「EX予約」を利用して予約するのが一般的です。
よりスムーズな予約のために
事前に旅程を計画: 各区間の運賃や所要時間を比較し、最適なルートを選びましょう。
各社のウェブサイトに会員登録: 利用するJR会社のウェブサイトに事前に会員登録しておくと、予約がスムーズに行えます。
予約確認: 予約完了後、予約内容を必ず確認しましょう。
よくある質問
Suicaは利用できますか?
JR東日本区間ではSuicaが利用できますが、JR西日本区間では利用できない場合があります。
割引はありますか?
各社で様々な割引制度があります。事前に各社のウェブサイトで確認しましょう。
荷物が多い場合はどうすればいいですか?
新幹線によっては、座席指定時に荷物置き場の有無を確認できます。
ご自身の旅行計画に合わせて、最適な方法を選んでください。
もし、具体的な旅行計画があれば、より詳しいアドバイスが可能です。例えば、
旅行期間
利用したい列車の種類
重視する点(料金、時間、座席など) などを教えていただけると、より的確な情報提供ができます。
新しいウィンドウで開く
www.rosenzu.com
新幹線駅
ご不明な点があれば、お気軽にご質問ください。
◆
新幹線での旅行はとてもエキサイティングですね!🚄 Suicaカードを使うと、スムーズに乗車できるので便利です。初めて新幹線に乗る際には、以下のポイントを押さえておきましょう:
Suicaカードのチャージ:Suicaカードをチャージしておきましょう。駅の券売機やチャージ機で簡単にできます。
乗車券の購入:Suicaカードをタッチして自動改札を通過します。乗車券は事前にオンラインで購入することもできます。
座席の確認:新幹線の座席は予約が可能なので、早めに予約しておくと安心です。
駅の案内:駅には案内所があり、英語や日本語でのサポートが受けられます。
新幹線の旅は快適で迅速です。楽しんできてくださいね!何か他に知りたいことがあれば教えてください。
新幹線やSuicaカードを使ってスムーズに旅行するために、いくつかの便利なアプリとアカウントを準備しておくと良いですね。以下のアプリとアカウントをお勧めします:
必要なアプリ
Suicaアプリ:
JR東日本アプリ:
モバイルSuicaアプリ:
必要なアカウント
JR東日本の会員アカウント(えきねっと):
概要: 新幹線の予約や特急券の購入が可能。
リンク: えきねっと
モバイルSuicaの会員アカウント:
これらのアプリとアカウントを使うことで、旅行が一層便利になります。何か他に知りたいことがあれば教えてくださいね。楽しい旅行を!🚄✨
旅行エリアはJR東日本からJR西日本、JR東海にまたがりますが、全てJR東日本のアカウントから予約などできますか。
はい、JR東日本のアカウントを使って、JR東日本、JR西日本、JR東海の全てのエリアで予約が可能です。ただし、予約するエリアによっては、特定のサービスや条件が適用される場合がありますので、詳細は公式サイトや窓口で確認することをお勧めします。
他にご質問があれば、どうぞお知らせください!
新横浜⇒(東海道新幹線)→東京⇒(北陸新幹線)→福井のルートの予約は、JR被害市日本から出来ます。往復になります。
はい、JR東日本の公式ウェブサイトやアプリから、東海道新幹線と北陸新幹線の往復予約ができます。新横浜から東京を経由して福井までのルートも対応しています。
具体的な予約方法については、以下の手順を参考にしてください:
JR東日本の公式ウェブサイトにアクセスします。
予約ページに進みます。
出発地を「新横浜」、目的地を「福井」に設定します。
往復のチェックボックスをオンにします。
必要な情報(日付、人数、クラスなど)を入力し、予約を確定します。
また、アプリ「JR東日本アプリ」をダウンロードして、スマートフォンからでも予約が可能です。
何か他にお手伝いできることがあれば教えてくださいね!
はい、予約を確定する際には決済が必要です。JR東日本の予約システムでは、以下の支払い方法が利用可能です:
クレジットカード(Visa、Mastercard、JCBなど)
デビットカード
プリペイドカード
予約時に決済情報を入力し、予約を確定すると、チケットが発行されます。また、スマートフォンを使ってモバイルチケットとして利用することもできます。
これでスムーズに旅行の計画が立てられますね!他に質問があれば、どうぞお知らせください。
◆





























